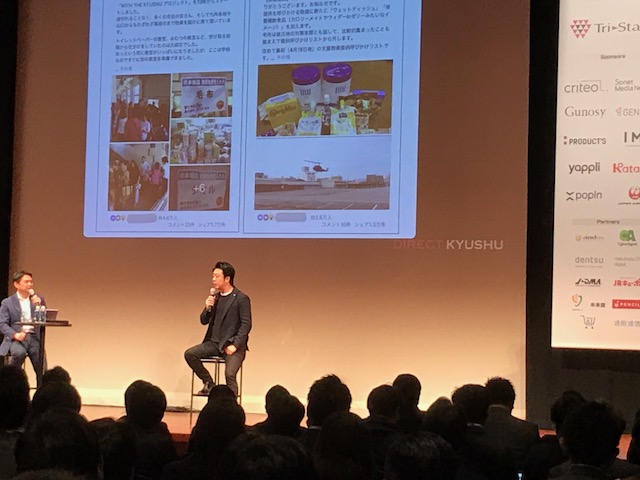独立型社会福祉士連絡協議会
こんにちは。
今日は独立型社会福祉士連絡協議会を行いました。
日本社会福祉士会から独立型社会福祉士としての質が担保されている福岡県の独立型社会福祉士名簿登録者12名で設立しました。
今後、独立型社会福祉士としての質の向上を目的とした勉強会や、独立型としての課題を整理し調査研究を進めていきたいと考えております。
本日の会合は2回目で、飯塚市でご活躍の藤岡弁護士を囲んでの座談会を企画しましたがあっという間の2時間で、次の会場予約のお客様もお待ちの中追い立てまくられるように会合を終えました。
明日は、某地域包括支援センターからご相談いただいている対応で飯塚へまいります。
要配慮者の食料・生活必需品
こんにちは。
そーしゃる・おふぃすへ入ってくる住まいの相談では、家電や家具など生活必需品をご自身で用意できない方も少なくありません。
その日の食料に困る方もおられます。
そういう場合は、連携している社協や生前整理・家財整理の業者さんへ協力いただいておりますが現状では不足しています。
住居を確保しただけでは、人間としての生活をすることはできません。
要配慮者(高齢者・障がい者・母子家庭・DV被害者など)の方々の生活再建に向けて、人として尊厳を持って安定した生活ができるよう地域の皆様方のお力をお借りしております。
要配慮者の方々へ食材(保存が可能なもの)はじめ中古の家電や家具の提供にご協力いただける方はそーしゃる・おふぃすへご連絡くださいませ。
一時的な支援はできるの?
こんにちは。
今日は、要配慮者の方へ物件を2つご見学いただきました。一つは駅・バス停・スーパー・病院 すべて徒歩圏内で、気に入っていただけたようでよかったです。
さて、そーしゃる・おふぃすには様々なご相談が入ってきますが、本日は入院を予定していて一時的な支援が欲しいとのご相談をいただきました。
私製契約で対応しております24時間緊急時対応付き見守り契約はいつでも解約ができますので身近に頼れる方がいらっしゃらない場合の一時的な支援についてもどうぞご利用くださいませ。
生活保護の方は、そのときに相談くださいね。
居住の権利を守るために
こんにちは。
今日は、小竹町の高齢福祉担当課・障害福祉課・まちづくり課と第2回目の会合の場を持ちました。
今回から、弁護士にも声をかけて参加いただきました。
住宅確保要配慮者の方々が、あたりまえに自分で住まいを選び、地域で暮らしていけるように課題整理と改善に努めていきます。
社会福祉士の倫理責任
こんにちは。
住宅セーフティネット法が改正されて1年が経過しました。量的調査は様々な機関により実施されているものの質的調査は行われていないと認識しています。
そこで、次年度は他専門職にもご協力いただきながら質的調査、つまり居住支援事業全体の効果検証を行っていきたいと考えております。
このことについて先日、社会福祉士の仲間に報告をしたところ、「社会福祉士にそんな実践研究やソーシャルアクションをやっている人はあまりいない」とその人は言いました。ほんとうにそうでしょうか。。。
そんなことはやっていないしできない、となれば社会福祉士の存在意義って何?となります。
もしかして社会福祉士不要論も噴出してくるかもしれません。
以下に社会福祉士の倫理責任について書きます。
社会福祉士には専門職としての4つの倫理責任が課せられております。
1.利用者に対する倫理責任
これは、利用者に対する説明責任・受容やプライバシーの尊重・権利侵害の防止について明記されています。
2.実践現場における倫理責任
ここには、他の専門職との連携協働・・業務改善の推進について明記されているものです。
3.社会に対する倫理責任
ここには、人々をあらゆる差別・貧困・抑圧・排除・暴力・環境破壊などから守り包含的な社会を目指すよう努める、つまりソーシャルインクルージョンの推進を課しています。さらに、社会にみられる不正義の改善と利用者の問題解決のため効果的な方法により社会に働きかけると明記されております。
4.専門職としての倫理責任
ここには、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信用を高めるとあります。
さらにさらに、社会保障審議会福祉部会でのご指摘によれば、社会福祉士の専門性は1、相談支援 2.他機関への橋渡し 3.社会資源の開発 この3つです。
上記から読み解くと、社会福祉士は自身の所属する組織の改善に留まらず、人々の権利侵害防止、社会問題の改善に向けたソーシャルインクルージョンの推進及び適切な方法で社会に働きかけていくことは、社会福祉士の義務であると捉えることができます。
できるできないは別としてまずは一人ひとりが問題意識を持つことがとても重要かもしれません。市場原理に従って問題意識の低い社会福祉士は社会から淘汰されるでしょ、と思うかもですが個人の問題では済まされなくなってきます。社会福祉士個人に対する評価は社会からの社会福祉士全体に対する評価につながってくるからです。そういう意味では、わたしも独立型として実践している立場で日々の緊張感は半端ではないわけで。。。。
立ち止まっている時間はありませんね。
成年後見制度は家族の負担軽減にも
こんにちは。
今日は、死後事務委任契約のご相談をいただきましたので、ご本人のご希望をお聞きして公正証書の説明をさせていただいております。
また、認知症が重度になってしまって生活に支障が出てきたということで、ご本人とご家族とでそーしゃる・おふぃすにご相談に来所なさいました。
ご本人を身近に支援しておられるご家族が一人で抱え込んでしまっておられる場合もありますが、成年後見制度を上手に活用していただければご家族の負担もかなり軽減できるかと思います。
「無理じゃないかな」「自分で頑張るしかない」と思う前に一度ご相談くださいね。
居住支援の1年を振り返る
こんにちは。
先週は連休前だったためか、某市役所・某社協・某母子生活支援施設、某地域包括支援センターから同時にばたばたと相談が入り、スタッフの社会福祉士とともに対応に追われておりました。浅田さん、ほんとにおつかれでしたね。
お子さんが小学生の場合は小学校区も考慮しなければなりませんし、仮にお母様に障害があったりすると、医療機関や勤務先にも配慮をする必要があります。
そんな中、本日土曜日は事務所で執筆作業に集中しました。
現在、高齢者住宅財団さまから原稿のご依頼をいただいております。
住宅セーフティネット法改正から1年、居住支援の取り組みについて雑誌エイジングインプレイス約5ページ分書き終えました。
この1年間、反省するところもありますが振り返る機会を与えてくださった高齢者住宅財団さまに感謝です。
そーしゃる・おふぃすの原稿はエイジングインプレイス4月号に掲載予定です。発行されましたら当HPでも公開させていただきます。
成年後見用診断書改定
こんにちは。
4月1日から成年後見用診断書が改定されることになりました。
本日付け福祉新聞から
最高裁は1月18日、成年後見制度の診断書を改定し、関係団体に通知した。
同制度の診断書は、2017年3月に閣議決定された同制度利用促進法で「医師が十分な判断資料に基づき判断ができるように本人の状況等を明確に伝えられる診断書の在り方を検討するとされたことを受け最高裁で検討してきた。
新たな診断書は、福祉関係者が持っている本人の生活状況等の情報を医師に伝えるツールとなる本人情報シートを作成するようにしたのが特徴。具体的には生活場所や要介護認定、日常・社会生活、認知機能、意思決定、金銭管理などの状況について、本人を支える福祉関係者が記載するようにした。新書式は裁判所のウエブサイトで4月1日以降公表される予定。